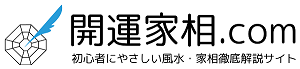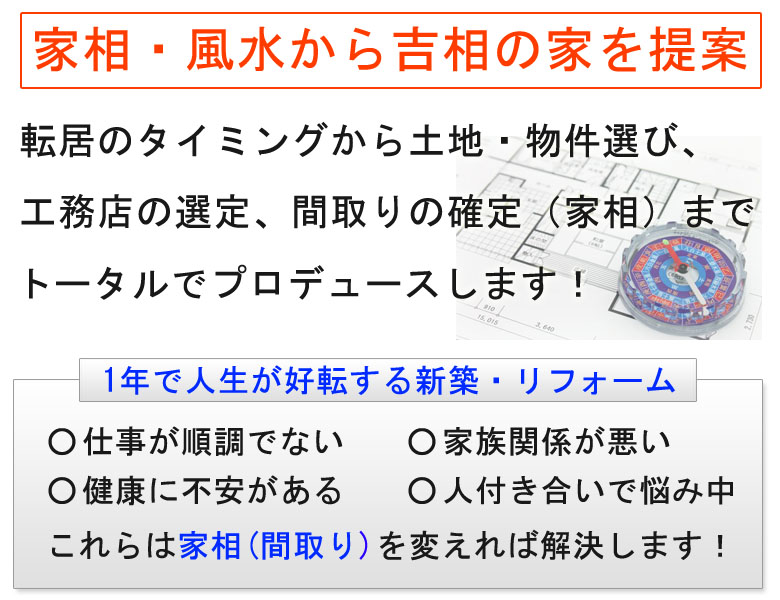「家相」という言葉を聞くと、「鬼門・裏鬼門・方位」「絶対に○○してはいけない」など、どこか厳格で“縛られる”イメージが浮かぶかもしれません。
建築会社や工務店の打ち合わせ時に問い合わせると「家相は科学的根拠がない迷信的」といわれた。とおっしゃるご相談者様が多くいらっしゃいます。
確かに縛られる必要はないと私も考えています。しかしながら、だからと言って単なる迷信と家相を完全に無視していいわけではありません。
家は「暮らし」「人生」を包む器です。風水・家相の知見を取り入れることで、安心・快適・開運につながる下地を整えることができます。
この二面を両立させてこそ、「縛られすぎずに、でもこだわるべきところを押さえた」家づくり・住まい方が実現します。今回はその観点でお話ししていきます。
1.「縛られすぎない」ことに共感する理由

家相=古くからの知恵だが、現代的な柔軟さも必要
家相という考え方は、「自然と調和し、気の流れを整えることで、家族が安心して暮らせる環境をつくる」という目的のもとに、長い年月をかけて先人たちが体感的に積み重ねてきた知恵の結晶です。
確かに、「鬼門」「裏鬼門」といった概念や、「この方位に○○を置くと運が下がる」といった言い伝えの中には、現代の科学でその正当性を証明するのが難しいものもあります。
そのため、一部では「迷信」や「根拠のない因習」として捉えられることもあるでしょう。
しかし、そもそも家相は“正しい・間違い”で測るものではなく、多くの人が“調子がいい”“居心地がいい”と感じる体感の積み重ねで実証され、それが脈々と受け継がれ、今でも語り継がれているという事実は、「実感として良さを感じる人が多い」という裏づけでもあります。
ただし、そういった知恵がいつしか「この方位を外すと危険」「決まりを守らないと不幸になる」といった、“縛るためのルール”のように誤解されることもあるのが現代の課題です。
そうなると本来の目的である「心地よく、安心して暮らせる家をつくる」ことから、かえって遠ざかってしまうこともあります。
だからこそ、家相の本質とは「縛ること」ではなく、“気の通り道”を整えることで、暮らしの巡りやすさ・家族の安定感をつくっていくこと。
現代においては、“決まりを守る”ことよりも、その背景にある意図や意味を理解しながら、柔軟に取り入れていく姿勢こそが、家相との心地よい付き合い方だといえるのではないでしょうか。
住まいには“快適性・機能性”が先行すべき
家づくりに家相の知恵を取り入れようとするとき、最初に戸惑う方が多いのが「家の中心の取り方」や「建物の形状の捉え方」に関する違いです。
実際、流派や鑑定者によって“家の中心の出し方”や“凹凸の判断基準”が異なることは少なくありません。
それによって「鬼門」「裏鬼門」の範囲や意味も微妙に変わってくるため、「家相は曖昧だ」「何が正しいのか分からない」と感じる方がいても不思議ではありません。
こうした背景から、
「家相に振り回されると、良い家にならないのでは?」
「間取りの自由度がなくなるのでは?」
という声もあるでしょう。

確かに、採光や通風、生活動線、構造的な安全性、水回りの使い勝手など、住まいの“快適性・機能性”を優先することは大前提です。
どれほど家相的に整っていたとしても、暮らしにくければ意味がありません。
だからこそ私は、
「あいまいに思える部分こそ、納得できる考え方を持った流派・鑑定士に依頼すること」がとても大切だと考えています。
家相の知恵は、決して万人に同じ正解を押しつけるものではありません。
その人の価値観や暮らし方、目指すライフスタイルに合った提案をしてくれる人と出会えることで、“縛られる家相”ではなく、“活かせる家相”へと変わっていきます。
心配より“対応策”を知ることで安心が生まれる
「縛られすぎない」という視点は、家づくりや間取り設計、インテリア選びの際に、必要以上に“家相に振り回されてしまう”ことを防いでくれます。
たとえば、「鬼門だから玄関は絶対にNG」「裏鬼門に子ども部屋を置いたら将来が心配」といった思い込みにとらわれてしまうと、本来は選択肢のある家づくりに、不必要な制限や不安を生んでしまうのです。
しかし実際には、鬼門に玄関があっても、裏鬼門に子ども部屋があっても、それだけで“悪い家相”と決めつけることはできません。
大切なのは、家全体のバランスをどう整えるか。
そして、必要な箇所にはしっかりと対応策や改善策を講じることです。
ところが近年、「これはダメです」と伝えるだけで、具体的な対応策を提案しない鑑定士が増えているのも事実。
それでは、家相は“縛り”や“制限”として受け取られてしまい、本来の目的である「心地よく、安心して暮らす家づくり」から遠ざかってしまいます。
家相の本質は、「こうしてはいけない」ではなく、「どうすれば、その人にとってよりよい暮らしの流れがつくれるか」という視点にあります。
だからこそ、構えすぎず、でも放置もせず、バランスを見ながら柔軟に取り入れていく姿勢が、最終的に心の自由や安心につながっていくのです。
2.それでもこだわるべき“家相・風水”のポイント

ただし、「縛られすぎない」という考えのみに終わると、家相・風水・家相的な視点を活かしきれず、せっかくの知恵を取り入れないまま終わってしまう可能性があります。以下のようなポイントは、ぜひこだわっておきたいところです。
家の中心や方位を完全に無視しない
「家の中心の決め方」や「鬼門・裏鬼門の範囲」があいまいだと感じる方も多いですが、これは流派によって家の中心の取り方や形状の判断基準が異なるためです。
そのため、「どの流派が正しいのか分からない」「結局、家相はあいまいだ」と感じられるのも無理はありません。
それでも、住まいを設計・配置する際に「方位」「建物の向き」「採光・通風」を意識することはとても大切です。
これらは家相や風水の基本である「気の流れ」を整える要素であり、結果的に住まいの快適性や健康的な環境づくりにも直結します。
例えば、南側に開口を多く設けて光と風を取り入れる、北側には湿気がこもりやすい水回りを避ける、といった配慮は、家相的にも理にかなった“暮らしを整える設計”です。
方位の考え方に違いがあるとしても、「気の流れを意識する」という根本の目的はどの流派にも共通しています。
だからこそ、最終的には自分が納得できる考え方・価値観を持つ流派や鑑定士を選ぶことが、安心して家づくりを進めるための第一歩となるのです。
水回り・玄関など “動線・陰陽・気の流れ” を意識

家相や風水の世界では昔から、「三備(玄関・キッチン・水回り)を鬼門・裏鬼門に配置してはいけない」という考え方が重視されてきました。
このような伝統的な教えに対して、「科学的な根拠が明確ではない」との指摘があるのも事実です。
しかし、玄関やキッチン、水回りといった場所は、水・汚れ・湿気・排気・風通しなど、実際の住環境に深く関わる重要なポイントです。
それゆえ、たとえ家相や風水に詳しくなくても、こうした設備の配置を考える際に「気の流れ」や「陰陽のバランス」「生活動線」を意識することは、機能的な住まいをつくる上でも非常に理にかなっているのです。
つまり、「風水的な象徴」としての鬼門・裏鬼門にとらわれすぎるのではなく、それらを“暮らしやすさのヒント”として柔軟に取り入れる視点が、現代における家づくりには有効だといえるでしょう。
メンタル・心理的安心のためにも「意味づけ」を
住まいは、ただの物理的な構造物ではなく、そこで暮らす人の心や日々の営み、家族の物語を包み込む“場”でもあります。
だからこそ、家相や風水を「ルール」として機械的に守るのではなく、「この家をどう建て、どんなふうに暮らしたいのか」という“意図”や“意味”を込めて設計していくことが、安心感や自己肯定感を育てる大きな鍵になります。
たとえば、
「この玄関は東南に開けて光を呼び込み、明るく人を迎える場所だから」
というように、自分なりの意味を持たせて暮らすことが、家そのものを“味方”にすることにつながっていきます。
もちろん、東や東南に玄関を設ければそれで万事OK、というわけではありません。
どんなに家相・風水が整っている家でも、住む人が何の努力もせず、何も工夫しなくても思い通りの人生が約束されるわけではないのです。
ただ、家相や風水の整った環境に身を置くことで、もし一見ネガティブな出来事が起きたとしても、「その出来事をどう捉え、どう成長に変えるか」という視点を持ちやすくなり、結果としてより良い展開へと進むことができます。
逆に、家相的に偏りや乱れのある環境に長く身を置いていると、ほんの些細な問題が実際に大きなトラブルへと発展しやすくなったり、不安感や停滞感を無意識に抱えてしまうというケースもあります。
だからこそ、家相・風水を取り入れる際には、「整えればすべてうまくいく」という依存ではなく、「よりよく生きるための土台を整える」というスタンスが大切です。
そのスタンスがあってこそ、「意味を持たせた住まいづくり」=「風水・家相を活かした暮らしの設計」が、住む人の心を支える力になってくれるのです。
「こだわり過ぎず、でも無頓着でもない」バランス感覚

家相や風水にあまりにこだわりすぎると、間取りの自由度が制限されたり、暮らしにくい家になってしまったり、場合によっては設計や工事のコスト・期間が大幅に膨らんでしまうことも確かにあります。
一方で、「そんなの気にしなくていい」とすべてを無視してしまうと、実際に暮らし始めてから体調不良や人間関係のトラブル、不安定な出来事が重なるなど、“なんとなくうまくいかない感覚”を抱えることも少なくありません。
だからこそ大切なのは、「どこまでを整えるのか」「何を優先するのか」という判断軸を持つこと。
まずは「日当たり」「風通し」「動線」「水回りの機能性」など、基本的な快適さと機能性をしっかり確保することが前提です。
そのうえで、家相や風水の知恵の中から「自分たちの暮らしにとって必要だと思えるポイント」を選び取って取り入れていく。これが、現実的で効果的な活かし方です。
こだわるところにはこだわり、ゆるめるところは柔軟に対応する。
そんなバランス感覚があってこそ、家相は「縛り」ではなく「味方」になります。
暮らしやすさと安心感、そして前向きな気の流れ。そのすべてを整えていくためには、“ちょうどいい距離感”がとても重要なのです。
3.まとめ:「開運家相」実践のためのステップ
-
住まいの基本条件を整える
・日当たり・風通し・水廻りの清潔さ・構造の健全性を最優先。 -
家相/風水の視点を“補助的”に取り入れる
・家の中心・方位(鬼門・裏鬼門)を意識。
・玄関・キッチン・水回りの位置に配慮。 -
意味づけと意図を持つ
・「この住まいで家族がこう暮らしたい」「こう成長したい」という意図を、間取り・配置・色・素材で表現。 -
こだわるべき点と妥協点を整理する
・無理に高額・過度な設計にしない。
・優先順位を設け、「これだけは譲れない」ポイントを決める。 -
定期的に見直す・改善する
・暮らし始めてから、風通しや日当たり・動線に改良が必要になることも。風水・家相は「建てたら終わり」ではなく、住みながら育てるものと捉える。
住まいをどう整えるかは、人生をどう生きたいかという問いとつながっています。
“縛られる”ではなく、“味方につける”と考えていきましょう。
家相や風水の知恵は、暮らしの中に、心地よさと意味を宿すことにつながり、住まいがあなたの人生を後押ししてくれる舞台になります。「気の流れ」を味方にすることで、あなたらしい未来が、いまここから始まっていきます。
家相(間取り)が変われば人生が好転する

これまで運がないと感じたり、どれだけ頑張ってもうまくいかなかったりすることはないでしょうか。
例えば仕事であれば、ブラック企業で働いていて収入や休みが少なく、労働時間が長いわりに給料は良くないことがあります。その場合、体が疲れ切っていて調子が悪いです。
また健康であれば、「脳梗塞になった」「がんと診断された」「ヘルニアになった」などを含め、何だか体調がすぐれないことがあります。
家族関係も大きな問題です。夫婦仲、息子、親、兄弟との関係が冷えていると家で過ごすプライベート時間が居心地の悪いものになります。他にも人間関係という意味では、上司・部下、同僚、ママ友、近所づきあいなども関わってきます。
こうした問題を抱えている人の家相・風水を私は長年みてきました。それらに共通することは、どれも家相が悪いということです。例えば仕事運のない人は「仕事で信頼されにくいとされる間取りの家」に住んでいます。健康に問題のある方は「健康を害しやすい家相の家」に住み続けています。
そこで家相(間取り)を変えれば、1年以内にそれまでの人生が好転するようになります。